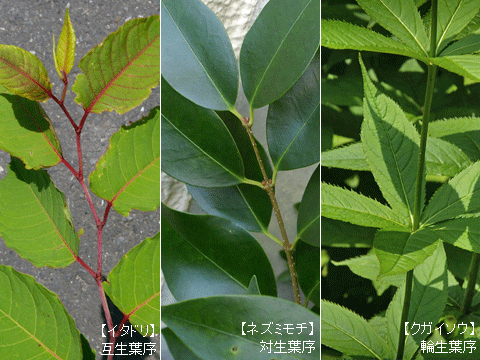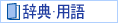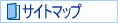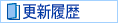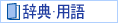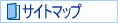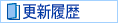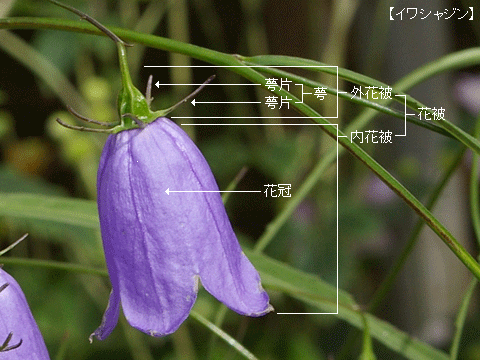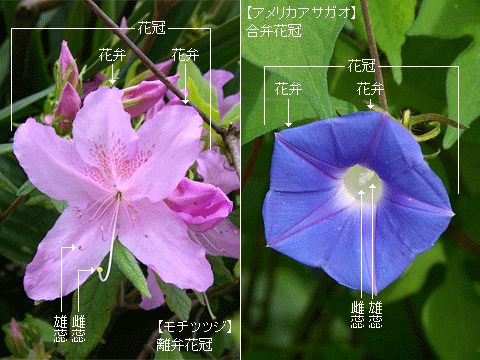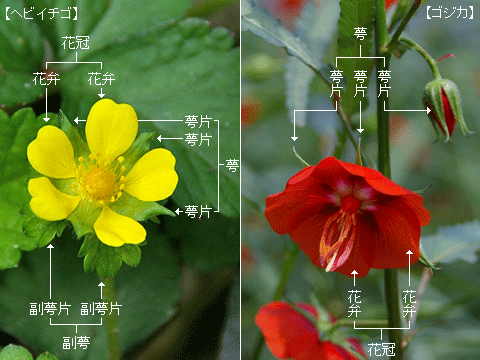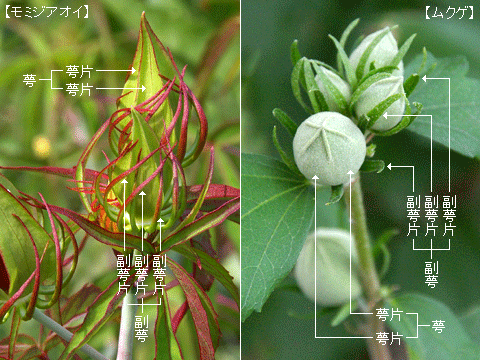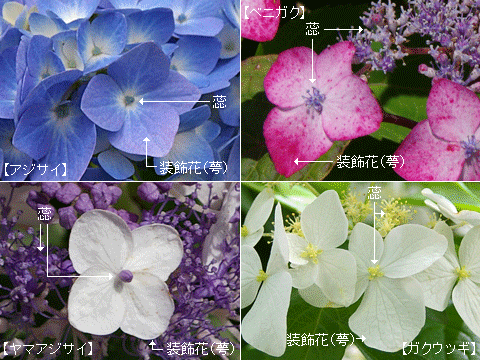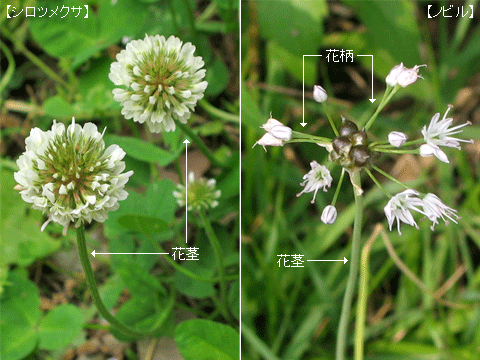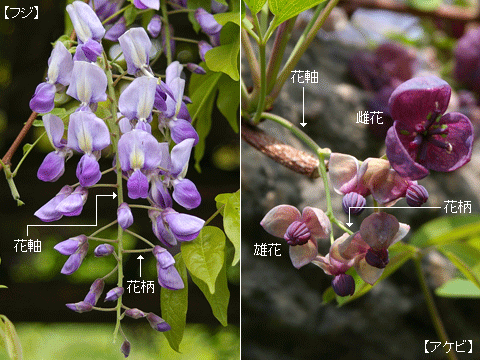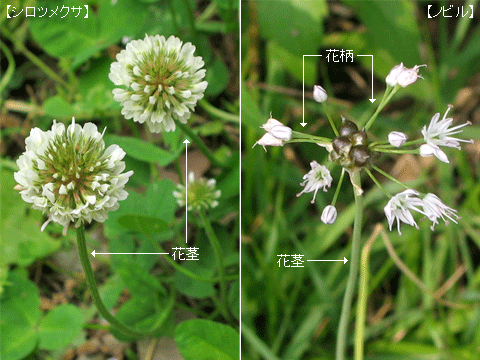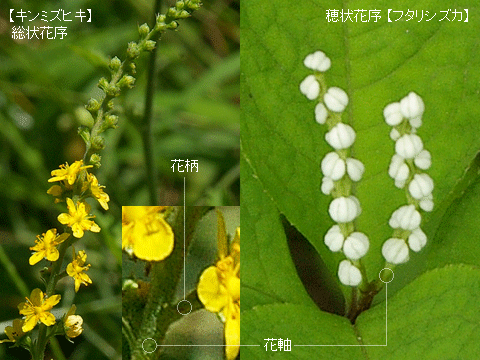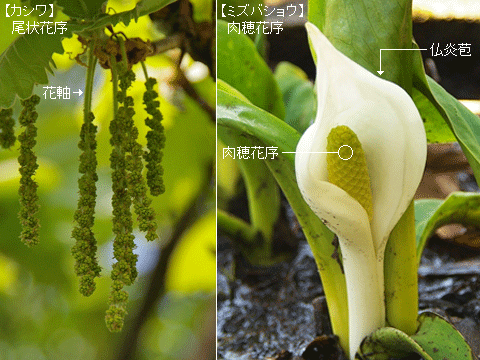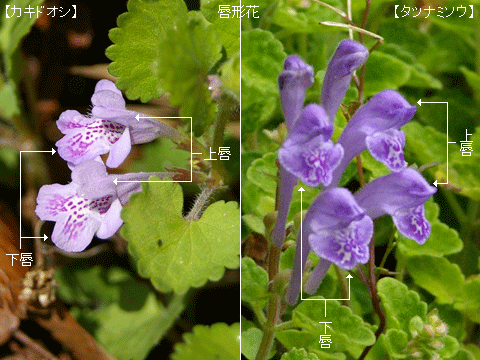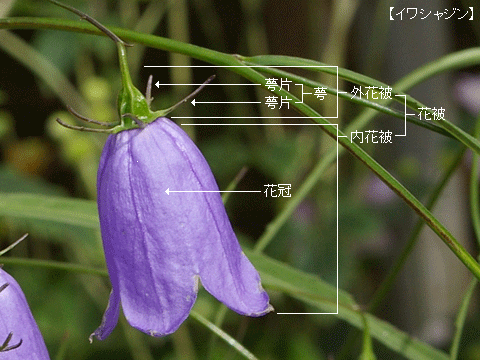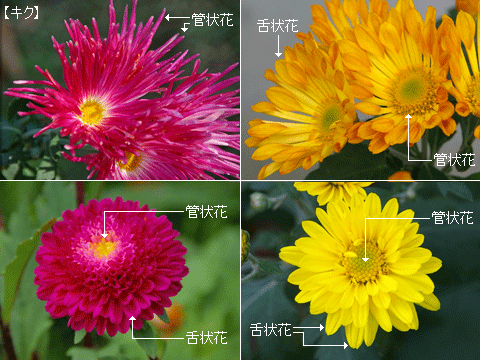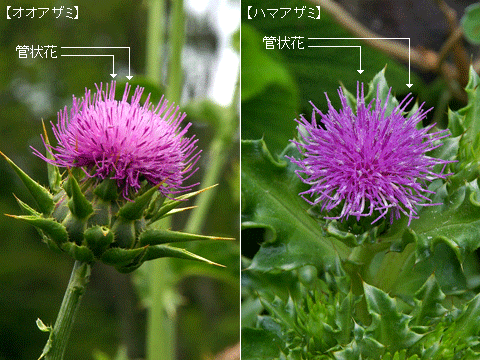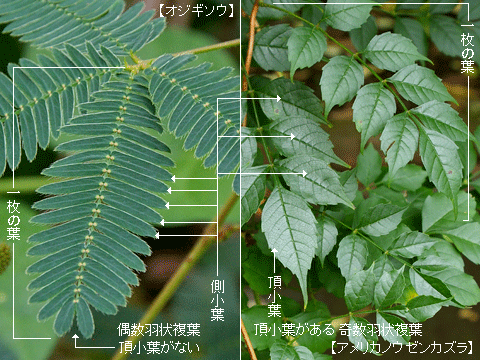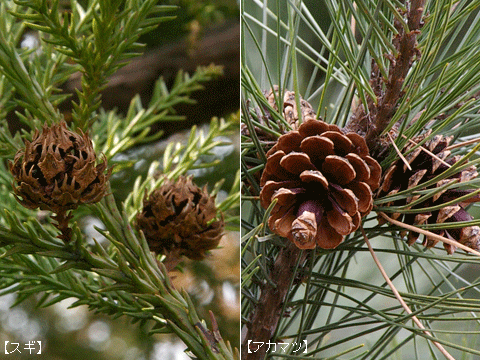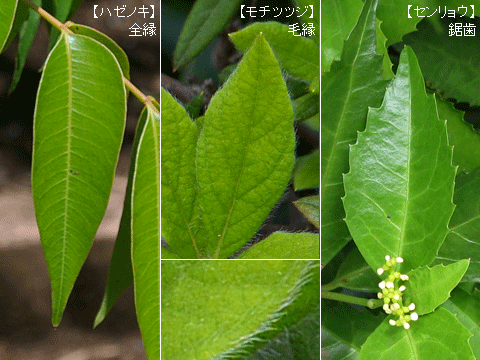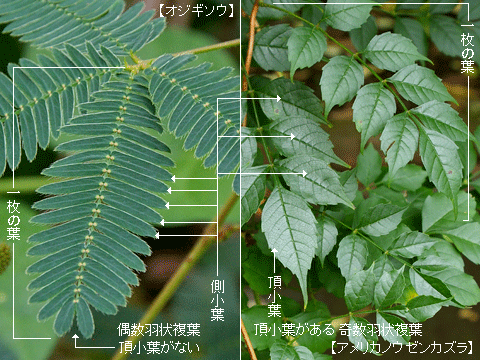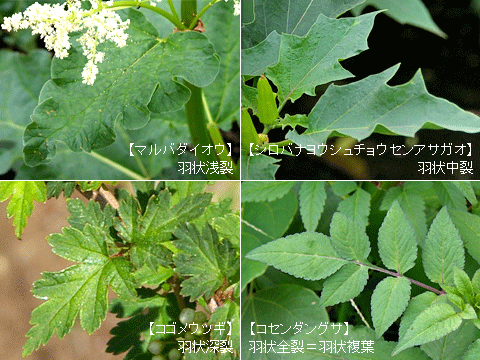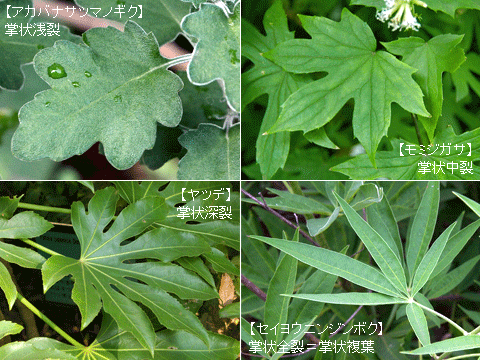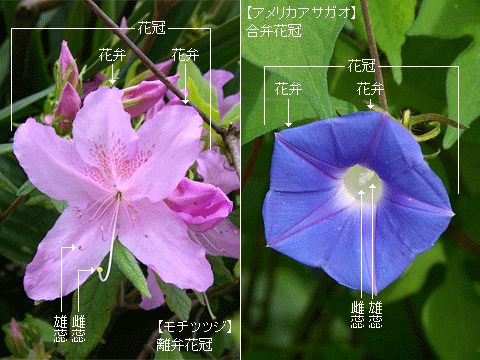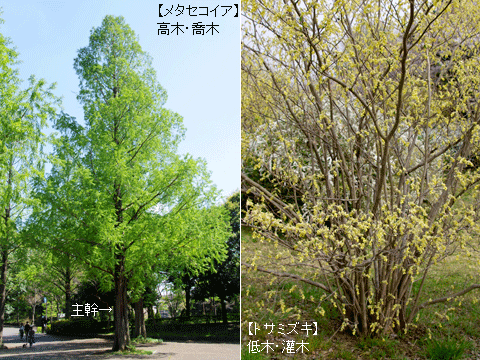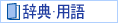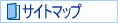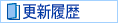外花被(がいかひ)
花冠(かかん)
雌蕊(めしべ、しずい)や
雄蕊(おしべ、ゆうずい)の外側にある部分の一枚一枚を、
花弁(かべん、一般には「花びら」)といい、それら花弁全体を、花冠といいます。
花冠は、雌蕊と雄蕊を保護する役目があります。
花冠は、
に区分されます。
更にその外側にあって、通常小さな葉の形をしているものを、萼(がく、萼の一枚一枚を萼片)といいます。
また、花弁に相当する部分を内花被(ないかひ)、萼に相当する部分を外花被(がいかひ)ともいいます。
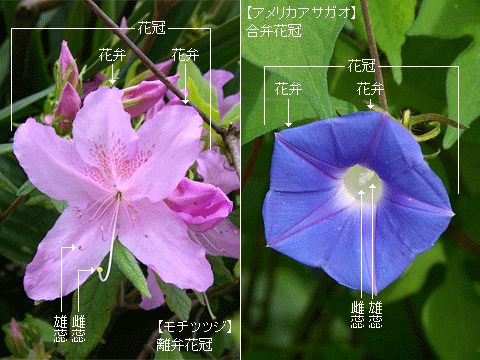
萼(がく)
花冠(かかん、花びら全体)の外側にある、通常小さな葉の形をしているもの一つ一つを萼片(がくへん)といい、この萼片を総称して、がく(萼)といいます。
萼には、花冠を下から支える役目があります。
この萼の外側に、更に、萼がある場合があります。これを
副萼(ふくがく)といいいい、その一つ一つを副萼片(ふくがくへん)といいます。
花冠と萼は、合わせて花被(かひ)と呼びます。
また、花弁に相当する部分を内花被(ないかひ)、萼に相当する部分を外花被(がいかひ)ともいいます。
萼に似た
苞(ほう)というものがありますが、萼は花冠を支える役を担うのに対して、苞は、開花前の蕾全体を包み保護する役を担います。
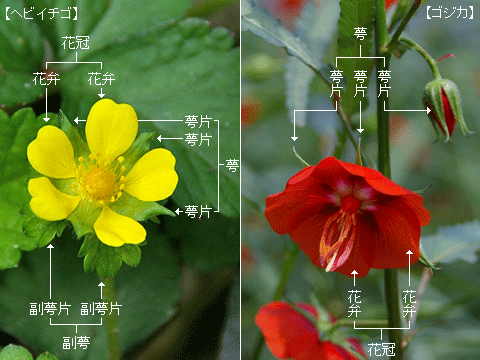
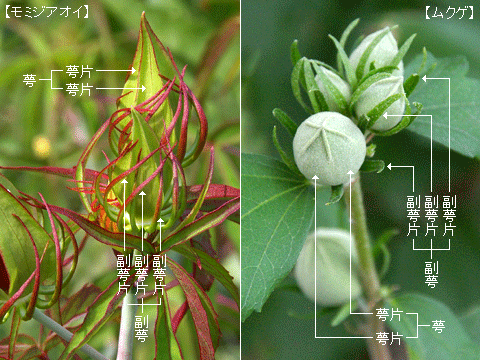
萼が、大きく発達して、花のように見えるものを、
装飾花(そうしょくか)といいます。
アジサイ、などがその代表的な例です。
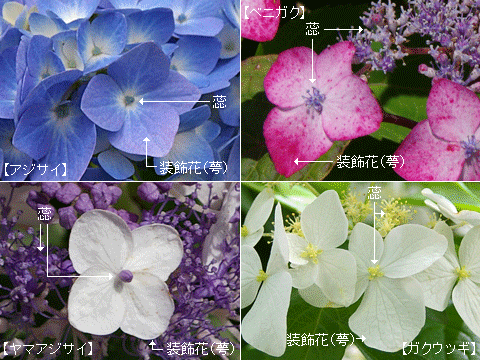
萼片(がくへん)
学名(がくめい)
植物の学名(scientific name)は「国際植物命名規約」によって定められ、ラテン語で表記します。
属名と種小名の組み合わせで学名とし、通常は斜体で表記します。
また、この学名で表現できない場合に、以下のような表記法を用います。
| 略号 | 用例(学名) | 和名 |
| cv. | Prunus kanzakura cv. Kawazu-zakura | サクラ '河津桜' |
|
「cv.」は園芸品種であることを表します。
「Kawazu-zakura河津桜」は、「カンザクラPrunus kanzakuraの園芸品種」、という意味になります。
また、「Prunus kanzakura 'Kawazu-zakura'、カンザクラ '河津桜'」のように、"'(シングルクォーテーション)"でくくることもあります。この方が一般的かもしれません。
|
| f. | Hydrangea macrophylla f. normalis | ガクアジサイ |
|
「f.」は品種であることを表します。
「ガクアジサイ」は、「アジサイHydrangea macrophyllaの一品種」、という意味になります。
通常は、色や形が異なる場合に区別するために用いられます。
|
| sp. | Citrus sp. | ミカン属の一種 |
|
「sp.」は「~属の一種」の意味になります。
「Citrus sp.」は、「ミカン属Citrusの一種」、という意味になります。
|
| spp. | Musa spp. | バナナ |
|
「spp.」は「幾つかある~属の一種」の意味になります。
「Musa spp.」は、「バショウ属Musaの幾つかある種の一つ」、という意味になります。
|
| subg. | Rhododendron subg. Hymenanthes | シャクナゲ |
|
「subg.」は「~属の亜属」の意味になります。
「Rhododendron subg. Hymenanthes」は、「ツツジ属Rhododendronに属するHymenanthesという名の亜属」、という意味になります。
|
| var. | Dianthus superbus var. longicalycinus | カワラナデシコ |
|
「var.」は変種であることを表します。
「カワラナデシコ」は、「ナデシコ類Dianthus superbusの変種」、という意味になります。
|
| x | Fragaria x ananassa Duchesne | オランダイチゴ |
|
「x」は交雑種であることを表します。
「オランダイチゴ」は、「オランダイチゴ属Fragariaとオランダのアナナス属ananassa Duchesneの交雑種」、という意味になります。
|
| L. | Alstroemeria pulchella L. | ユリズイセン |
|
「L.」は命名者名で、スウェーデンの植物学者Carl von Linneです。
「ユリズイセン」は、「植物学者Carl von Linneが命名した」、という意味になります。
|
| Makino | Aster savatieri Makino | ミヤコワスレ |
|
「Makino」は命名者名で牧野富太郎です。
「ミヤコワスレ」は、「牧野富太郎によって命名された」、という意味になります。
|
| Thunb. Nakai | Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai | センリョウ |
|
「Thunb.」は原命名者名でスウェーデンの植物学者Carl Peter Thunberg、「Nakai」は命名者名で中井猛之進です。
( )は原命名者名を表し、「センリョウ」は、「Carl Peter Thunbergによって命名された学名を、中井猛之進によって変更された」、という意味
|
花茎(かけい)
花だけを付ける茎(くき)を、
花軸(かじく)といいますが、そのうち、(枝や茎から枝分かれしたものではなく、主に草本で)直接地面から伸びる茎に花だけが付く場合に、この茎を花茎といいます。
途中で枝分かれしたり、葉が付くことはありません。
この花茎から枝(柄)を出し、その先に花が付く場合は、花を支える枝(柄)を、
花柄(かへい)といいます。
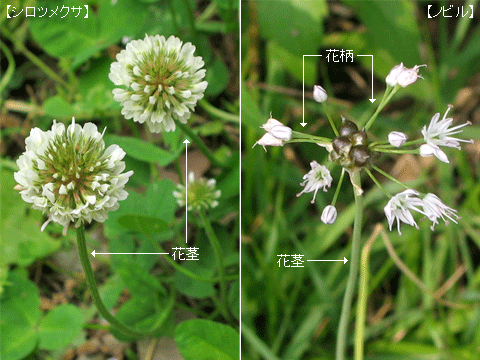
花糸(かし)
花軸(かじく)
花だけが付く茎や枝を、花軸といいます。
途中で枝分かれしたり、葉が付くことはありません。
花軸のうち、特に、(枝や茎から枝分かれしたものではなく、主に草本で)直接地面から伸びる茎に花だけが付く場合に、この花軸を
花茎(かけい)といいます。。
この花軸から枝(柄)を出し、その先に花が付く場合は、花を支える枝(柄)を、
花柄(かへい)といいます。
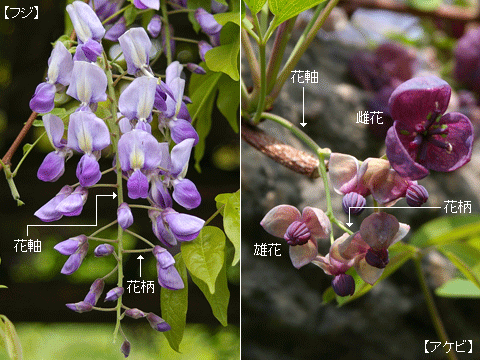
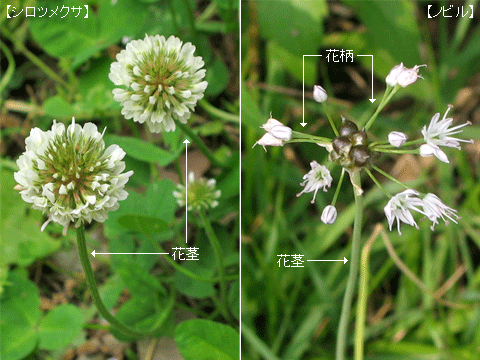
花序(かじょ)
(この項は編集途中です)
花のつき方を分類するための言葉です。
分類の方法は幾つかあるのですが、以下の二つに大別されます。
- 無限花序(むげんかじょ)、或いは総穂花序(そうすいかじょ) ----- 花軸(かじく)の基部から先端に向かって(直立する場合は下から上へ、垂下する場合は上から下へ)、順次咲いて行きます。
- 総状花序(そうじょうかじょ) ----- 花軸に沿って花柄(かへい)を出し、その花柄の先に花を付けるもの
- 穂状花序(すいじょうかじょ) ----- 花軸に沿って花を付けますが、花柄がなく、花軸に直接花が付くもの
- 尾状花序(びじょうかじょ) ----- 穂状花序の中で、下垂するもの
- 肉穂花序(にくすいかじょ) ----- 穂状花序の中で、花軸が多肉質のもの
- 有限花序(ゆうげんかじょ)、或いは集散花序(しゅうさんかじょ) ----- 花軸の先端に花を付け、基部の方に向かって(直立する場合は上から下へ、垂下する場合は下から上へ)、或いは、外側に向かって広がるように、順次咲いて行きます。
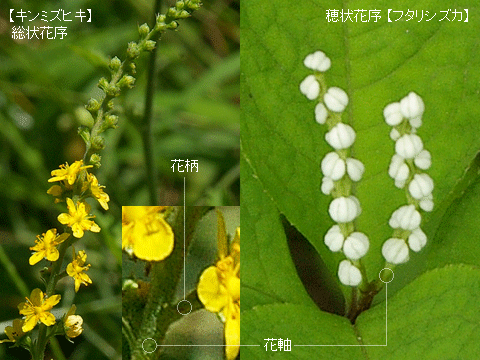
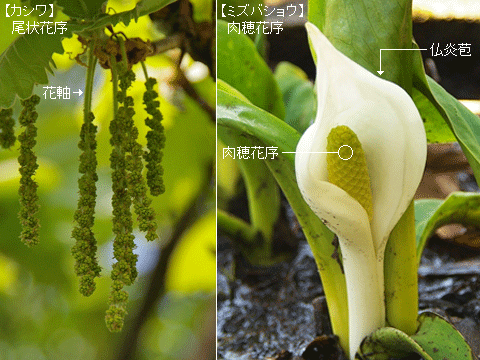
下唇(かしん)
花弁(かべん、花びら)が筒状で、その先が上下に別れた花を、唇の形をしていることから
唇形花(しんけいか)と呼びますが、その下の部分を下唇といいます。
これに対して、唇形花の上の部分を上唇(じょうしん)といいます。
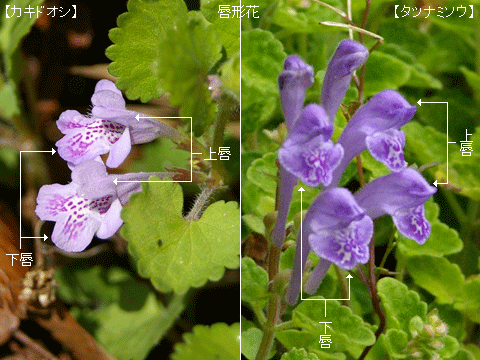
花穂(かすい)
花柱(かちゅう)
花被(かひ)
花柄(かへい)
茎や枝から伸びて、花を支える役目をする枝を、花柄といいます。
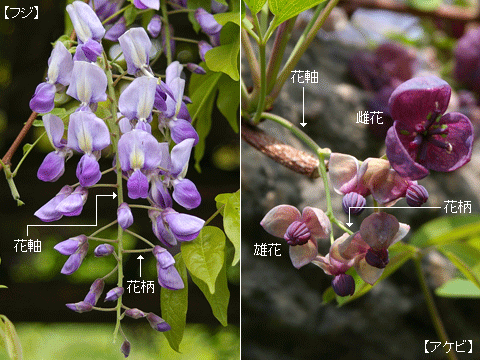
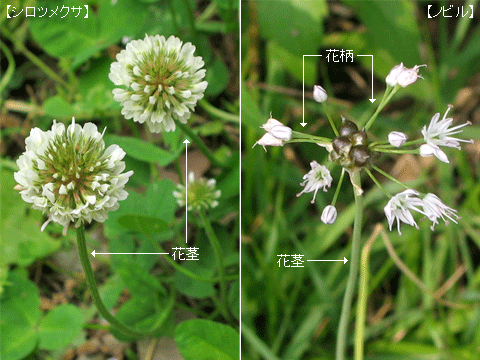
花弁(かべん)
管状花(かんじょうか)
灌木(かんぼく)
奇数羽状複葉(きすううじょうふくよう)
一枚の葉が
全裂((ぜんれつ)して、複数の独立した葉のように見える葉を複葉といい、その一つ一つの葉を小葉(しょうよう)といいます。
この小葉は、全体が一枚の葉のように(本来は一枚の葉ですので当然といえば当然ですが)、平面上に並びます。
この小葉が三枚以上で、羽状に並ぶものを、
うじょうふくよう(羽状複葉)といいますが、その内、
頂小葉(ちょうしょうよう、先端の対にならない小葉)があるものを、奇数羽状複葉(きすううじょうふくよう)といいます。
頂小葉がないものは、偶数羽状複葉といいます。
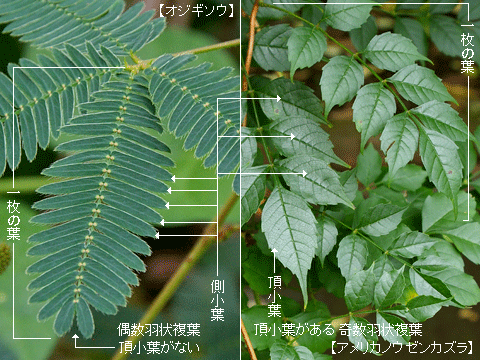
旗弁(きべん)
マメ科などに多く見られる蝶のような形の
蝶形花(ちょうけいか)の一部で、上に立ち上がる形の花弁を、旗弁といいます。
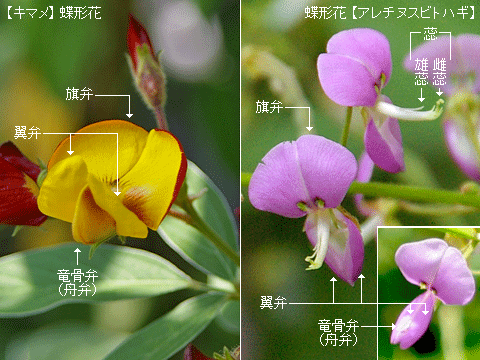
毬果・球果(きゅうか)
木質化した鱗片が重なって球状になったものを、毬果・球果といいます。
中に種があります。
マツ科の球果は、特に「松かさ」とか「松ぼっくり」とか呼ばれます。
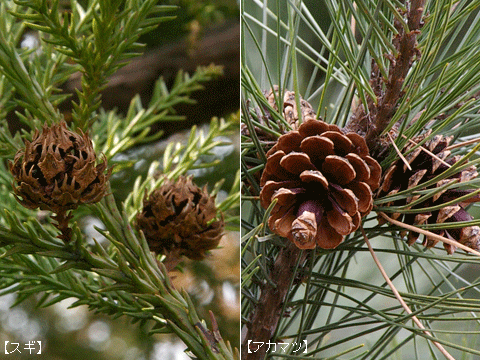
喬木(きょうぼく)
鋸歯(きょし)
葉縁(ようえん)の分類の一つで、葉の縁に鋸の歯状のギザギザがあるものを、鋸歯といいます。
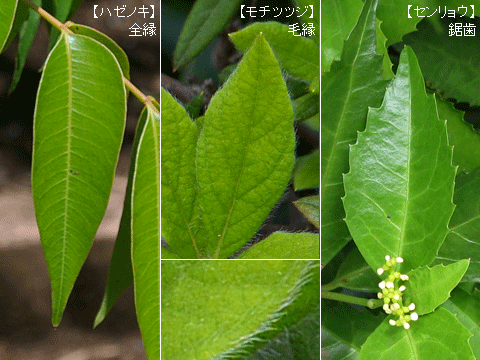
偶数羽状複葉(ぐうすううじょうふくよう)
一枚の葉が
全裂((ぜんれつ)して、複数の独立した葉のように見える葉を複葉といい、その一つ一つの葉を小葉(しょうよう)といいます。
この小葉は、全体が一枚の葉のように(本来は一枚の葉ですので当然といえば当然ですが)、平面上に並びます。
この小葉が三枚以上で、羽状に並ぶものを、
羽状複葉(うじょうふくよう)といいますが、その内、
頂小葉(ちょうしょうよう、先端の対にならない小葉)があるものを、偶数羽状複葉(きすううじょうふくよう)といいます。
頂小葉があるものは奇数羽状複葉といいます。
これに対し、全裂していない葉を単葉(たんよう)といいます。
全裂した複葉なのか単葉なのかを区別するのは、難しいのですが、幾つかの葉が同じ平面上にあるものは、複葉の可能性が高いですね。
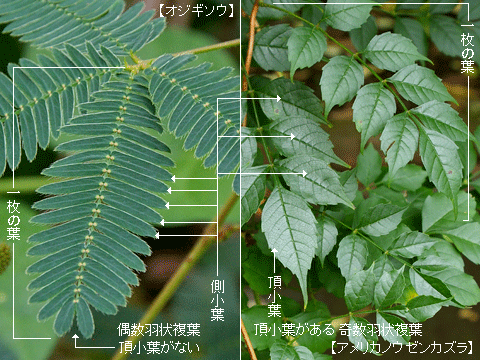
欠刻(けっこく)
葉の切れ込みをいいます。
欠刻は、切れ込みの深さから、
に分類され、更にその形状から、
に区別されます。
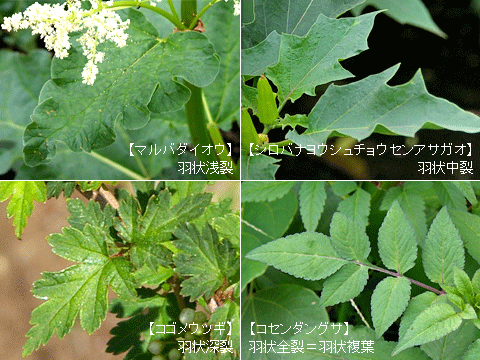
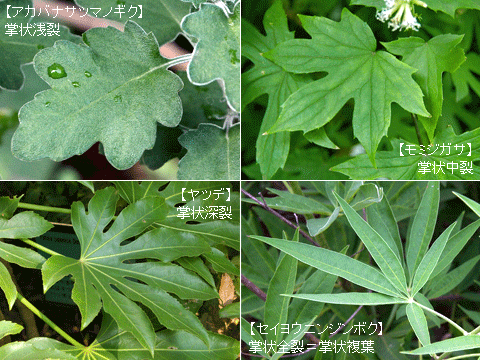
合弁花(ごうべんか)、合弁花冠(ごうべんかかん)
高木(こうぼく)
高さが二~三m以上になる樹木で、幹が直立し、その幹から枝を張るもので、喬木(きょうぼく)ともいいます。
樹木を高さで区別する際の目安ですが、明確な定義はありません。
サクラやヒノキなどがあります。
これに対し、高さが約二~三m以下の樹木を低木(ていぼく)といい、主幹がはっきりせず、根元から何本かの枝を出すもので、灌木(かんぼく)ともいいます。
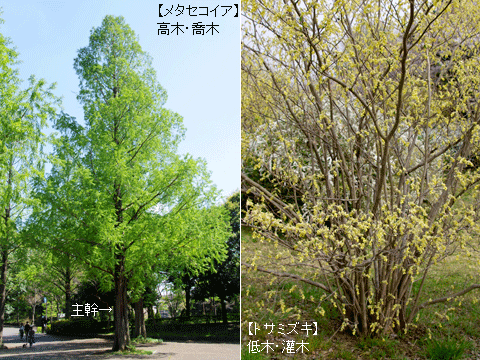
互生葉序(ごせいようじょ)、互生(ごせい)
茎に対しての葉の付き方を、
葉序(ようじょ)といいますが、このうち、茎から交互に葉が付くものを、互生葉序(一般には互生)といいます。